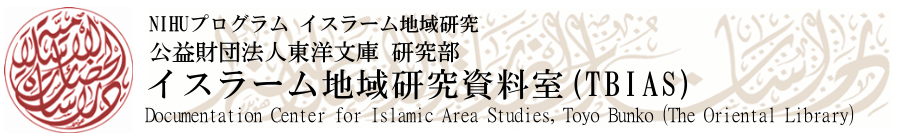第23回中央アジア古文書研究セミナー(2025/3/15~16)報告
アゼルバイジャン ウズベキスタン ロシア 中央アジア・コーカサス 中央アジア古文書研究セミナー
第23回「中央アジア古文書研究セミナー」を、下記の要領で開催いたしました。
日時: 2025年3月15・16日(土・日)
場所: 京都大学文学研究科附属文化遺産学・人文知連携センター羽田記念館(京都市北区大宮南田尻町13)、オンライン(Zoomミーティング)
【プログラム】
15日(土)
13:30~13:50 参加者自己紹介
13:50~15:50 塩野崎信也(龍谷大学文学部)
「離婚裁判文書にみるザカフカースの宗務管理局とシーア派法学」
16:10~17:10 杉山雅樹(京都外国語大学共通教育機構)
「道路利用に関するサマルカンドのファトワー文書(1):文書本文」
17:10~18:00 質疑応答
*司会:磯貝真澄(千葉大学大学院人文科学研究院)
18:30~ 懇親会
16日(日)
11:00~12:30 杉山雅樹
「道路利用に関するサマルカンドのファトワー文書(2):文書本文」
13:30~15:00 磯貝健一(京都大学大学院文学研究科)
「道路利用に関するサマルカンドのファトワー文書(3):典拠学説」
15:15~16:30 質疑応答・総合討論
*司会:矢島洋一(奈良女子大学研究院人文科学系)
【報告】
2025年3月15〜16日、第23回中央アジア古文書研究セミナーが京都大学大学院文学研究科附属文化遺産学・人文知連携センター(羽田記念館)において開催された。本セミナーは科研費(基盤研究(B))「ロシア帝国領中央ユーラシアにおける家族と家産継承」(代表:磯貝健一)の助成によるものである。例年同様、対面とオンライン(Zoomミーティング)を組み合わせたハイブリッド形式で実施され、対面で16名、オンラインで10名の計26名が参加した。磯貝真澄氏(千葉大学)による進行のもと、参加者の自己紹介があり、その後、塩野﨑信也氏(龍谷大学)、杉山雅樹氏(京都外国語大学)、磯貝健一氏(京都大学)による文書の講読と解説、そして質疑応答が行われた。

塩野﨑信也氏のセッションでは、ロシア帝政期の南東コーカサスにおける婚姻事件にかんする文書(アゼルバイジャン国立歴史文書館所蔵)を扱った。この事件は、原告である妻が、夫との婚姻関係が無効であることを訴えたものである。この事件をめぐって宗務管理局から郡カーディーに送付されたペルシア語文書(講読時は講師による翻刻を使用)が今回の講読対象であった。夫が宣誓を延期して事件を長引かせようとすることを承けて、宗務管理局が郡カーディーに対して早急に対応するよう求めるというのが講読文書の内容であった。講読文書を通じて、当事者、郡カーディー、県メジュリス、宗務管理局の間で多くの書類がやり取りされていた状況が判明し、三審制の中で婚姻事件がどのように扱われていたかが垣間見えた。
杉山雅樹氏のセッションでは、ロシア帝政期中央アジアにおける道路利用をテーマとしたファトワー文書2点(サマルカンド州立郷土博物館所蔵)を扱った。2点とも本文はペルシア語、ファトワー典拠文はアラビア語であった。1点目は、共有者の許可無く袋小路に庇を設置した人物に対して、庇の撤去を求めるファトワー文書であった。2点目は、自身の邸宅を売却した人物がかつての自身の邸宅の処遇をめぐって妨害行為を行なっていることを不当だと訴えるファトワー文書であった。この事件はロシア帝政期の道路拡幅政策が発端となっているが、文書本文では中央アジア統治を担うトルキスタン総督(ひいては最高権力者であるロシア皇帝)を指して「パーディシャー」という語が用いられている点が興味深かった。

磯貝健一氏のセッションでは、杉山氏のセッションで扱った2点の文書に引用される法学説について、引用元の法学書に立ち返って引用箇所の前後の部分と一緒に講読した。文書という「実践」面だけではなく、法学書という「理論」面もカバーするという、例年に無い新しい試みであった。今回は法学を専門とする参加者が例年以上に多かったということもあり、法学書テキストの内容について活発な議論が交わされた。
本セミナーはアラビア文字の古文書の読解について学ぶことのできる貴重な場であると同時に、イスラーム法学、制度史、社会史、地域史といった様々な分野を専門とする参加者が一同に会し、最新の知見を交換する機会でもある。このような素晴らしいセミナーを開催するために尽力し、講師・司会を務めてくださった磯貝健一氏、磯貝真澄氏、塩野﨑信也氏、杉山雅樹氏、矢島洋一氏に改めて感謝を申し上げたい。
(文責:笹原健・京都大学大学院文学研究科博士後期課程)
(2025年4月6日更新)